2020/8/27讀賣朝刊の記事。
有名な日本酒「獺祭(だっさい)」を作っている山口県の旭酒造の会長の「日本酒新時代」というコラム。

今のように日本酒の「吟醸」「純米」「純米吟醸」などが出る前は、特級酒・1級酒・2級酒と区別されていました。これは酒税法の区分で、簡単に言うとアルコール度数に基づいて酒税の税率の高い順でした。旨いとか不味いとか純米とか製法とか関係無かったのです。
このナンセンスな酒税法は1993年まで続いており、それ以前は旭富士とか越乃寒梅とか銘柄酒はあるにはあっても、地元の酒蔵直売か酒蔵周辺の地元の酒店でしか買えないものでしたので「地酒」と言われ、広く流通していませんでした。この新聞のコラムはその酒税法改正後に日本酒の「地酒ブーム」を作り出した代表と言える獺祭の誕生ストーリーです。
その中に注目すべきポイントがありました。モノ作りメーカーにとって大切なポイントです。

旭酒造では、酒税法改正をにらんで1980年代に純米吟醸の無濾過で「雪化粧」という銘柄の酒を発売し、大手百貨店やスーパーなどで販売してそこそこ売れたそうです。そしたら同じような無濾過の純米酒や吟醸酒が出てきて売れ行きが陰った時、スーパーの担当者から
「すぐに売れなくなるので次の企画を考えて」
と言われたそうです。でも旭酒造の会長は「これじゃダメだ。このマーケットでは常に新しい商品を出し続けないといけなくて、それに付き合うと疲弊してしまう」と考えたそうです。
そこで大手量販店向けではなく、理解のある都内の酒屋24軒のみ向けにプライベートブランドで「獺祭」を1990年に発売したそうです。
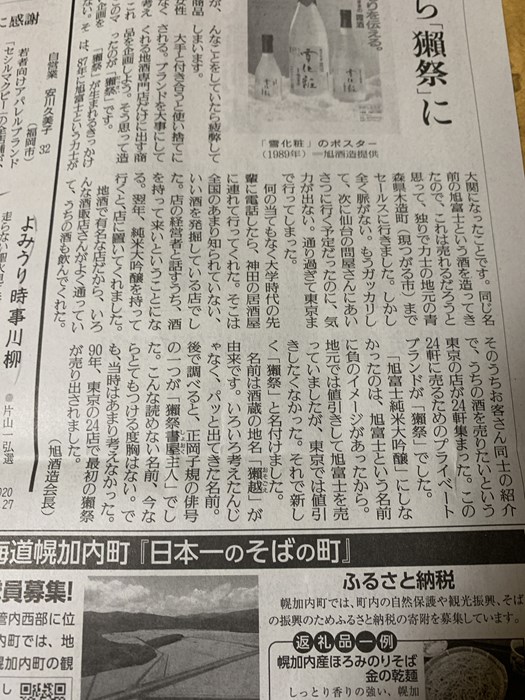
そして獺祭は、地酒・高級日本酒の代名詞と言える地位を築き、30年後の今も売れています。
モノ作りメーカーにとって大切なポイントとは、
【商品を育てて長く売ろうせず、商品を使い捨てにする販売者とは付き合わない】
です。
大手になればなるほどバイヤーの質が落ちる傾向があります。バイヤーは本来「目利き」であるはずですが、サラリーマン化して目利きの能力が低くなり、新たな商品の発掘能力が無いので売れた商品の「まねっこ次のシリーズ」を要求するのです。ようは「売るための努力」を自らがせず、「企画」だよりになっているのです。
こういうバイヤーに付き合っていると、メーカーが努力して作った商品が使い捨てにされます。
「ある商品を売った」→「売れた」→同種商品の乱立(ここには当該バイヤー自身が他の納入先に「これ売れてるんだよねー」みたいな一種の情報漏洩が常にあります)→「売れなくなる」→「同シリーズの次の商品を発売」→「そこそこ売れた」→同じ循環サイクル・・・・
これ、ダメ。
メーカーにとって販社のバイヤーはキーパーソンですが、相手を見極めて付き合わない事も必要です。