今回は、画像ほぼ無しの長文ですので、ヒマな方・興味のある方だけお読み下さい。
バスケを応援するPhilip College Ringとしては、会場であるアリーナの整備こそが日本バスケ発展の重要キーポイントだと考えています。今、アリーナの捉え方考え方、建設、運営などは実業団・学生バスケ主流だった時代からプロバスケへの移行期間なので、紆余曲折中です。
以前のアリーナとはイコール体育館でした。
天皇杯レベルの全国大会でも、会場は東京体育館など「公営体育館」で行われており、1F座席はフロアに置いた折畳みいす、2F座席は数列しかないお尻が痛くなる固定椅子。これ、当たり前の状況でした。
そのバスケ会場の常識を打ち破ったのが旧bjリーグ。
ファイナルを有明アリーナで行い、コートサイドのエキサイティングなシート、ゴール裏の熱烈ファン向けシート、VIPルーム出入り可能な高額シートなどなどNBA並みとはいかなくても、それをお手本にしたエンターティンメント性を追求した各種シートを導入しました。応援の仕方も、相手チームのフリースローへのブーイングなどブースター(ファン)が一体化する観戦を提案。グッズ売り場、飲食店舗も従来の公営体育館で行われるゲームとは格段に違う充分充実したものでした。
当時は、bjリーグ決勝戦がようやくBS放送される程度で新聞のスポーツ欄にも結果が報じられない認知度のリーグが、有明アリーナを貸し切り、またそこを1万人規模で満員にした事は、日本バスケの夜明けを感じたものです。
2016-17シーズンに発足したB.LEAGUEは、最初の決勝戦の会場を「バスケの聖地」代々木体育館にしました。もちろん、ワタクシ足を運びました。ゲームは見ごたえのある白熱したものでしたが、アリーナの観客動線、飲食・物販施設、トイレなどは有明アリーナのbjファイナルとは比較にならない退歩でした。
これはリーグの運営の問題ではないのです。
アリーナの設計思想、所有者の考え方・捉え方、規定の問題なのです。
東京オリンピックに向けて全面改装中の有明アリーナは、東京都営です。
東京都所有の有明アリーナは、当初からコンサートなどエンターティンメント興行に貸出しており、物販飲食サービスの臨時施設設置に前向きな考え方でしたので、bjファイナルも観客にとって心地よいものでした。
代々木体育館は、1964年の東京オリンピックに向けて建設されたアリーナで国立。
(当時は)アマチュア競技の祭典だったオリンピックの精神そのものに、物販飲食サービスなどのエンターティンメント要素を一切排除し、単に大勢の人々がすし詰めの席で競技を見て応援する・・・・為だけの施設で、この21世紀になってもそのままの「ガラパゴス」でした。
現在存在する公営アリーナは、エンターティンメントOK型とNG型の二つに大きく分かれています。
B.LEAGUE2年目の2017-18ファイナルが行われた横浜アリーナは、市営ですが、やはり各種コンサートなどを受け入れているので、OK型でしたから初年度のファイナルより断然居心地がよかったです。
千葉ジェッツの本拠地、船橋アリーナは市営で施設の設計思想はNG型の典型ですので観客移動動線は宜しくありませんが、運営思想は千葉ジェッツの島田社長に感化されたものか、エンターティンメント大歓迎型。
しかし、OK型アリーナもそもそもの設計思想が、エンターティンメント性を排除した古臭い設計なので、結構ムリ無理興行ってのが実態です。
そこに公営アリーナながら「理想のアリーナ」となりそうな計画が具体化しました。
「沖縄市多目的アリーナ」
現在の沖縄市体育館ですが、ワタクシ数年前にキングスの開幕戦を観に、この沖縄市体育館に行きました。このアリーナは公営体育館そのものの古臭い、日本中どこにでもある体育館でしたが大変身を遂げそうです。
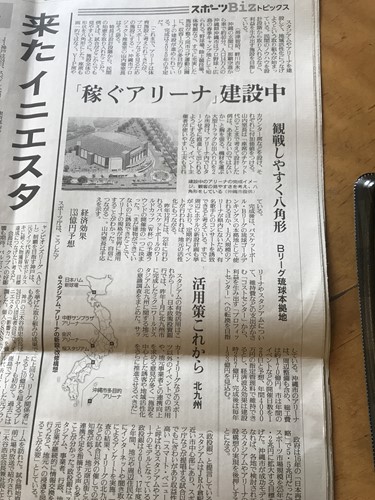
写真では記事の内容まで読めませんね。
以下、抜粋。
場所は那覇空港から車で40分の沖縄本島中部、人口14万人の沖縄市。
建設設置主体も沖縄市で2020年完成予定。
収容人員1万人。
B.LEAGUE琉球ゴールデンキングスのホームとして使用され、県内にこのような規模のアリーナが無い為、コンサートなどでも活用されるのは必至。
そして大注目は、その設計思想。
バスケなどフロア中央で行われる競技が見易いように八角形の構造。座席も画一的では無く、VIP席やカウンター席などプロ野球スタジアム並みの各種シートを設計段階から料金体系も含めて盛り込んでおり、設定段階で集客=収益が勘定出来るという、民間ホテルなどなら当たり前の商業的設計思想。
プロバスケやコンサートなどのエンターティンメントを支える機材搬入の裏動線設計でも、トラックヤードでUターンせずに設備の搬出入が出来る設計との事。
これ、きっとキングスの木村社長がイニシティアブを取っているものと思われます。
更に周辺にホテルの計画も立ち上がっており、人口14万人の小規模都市にとって絶大な地域活性化効果があるでしょう。
記事には乗っていませんが、もちろん課題もありそうです。沖縄県はごく一部のモノレール以外、公共輸送機関が発達していません。沖縄本島の人口密集地は、もちろん那覇市・宜野湾市など島南部です。アリーナがある沖縄市は、島中部の山間部にあり、アクセスは車orバスしかありません。沖縄本島を南北に縦断する沖縄自動車道の沖縄南インターからすぐの立地ですので、車アクセスは容易です。しかし、1万人規模を満員にするには3000~5000台もの駐車場が必要になります。
ざっとネットで大きな規模の駐車場を調べてみました。
東京ベイららぽーと4600台
イオンモール幕張 7300台
成田空港 3100台
羽田空港 9570台
1日20万人が利用する羽田空港が日本最大の駐車場キャパシティを誇っています。首都高湾岸線で羽田を通過した事のある人は見た事があると思いますが、巨大な倉庫や空港ターミナルビルが立ち並ぶ羽田周辺で最も威容を誇っているのは、湾岸線両側にそびえたつ4っつの巨大駐車場の建物です。
沖縄市立体育館は、公共公園の「コザ運動公園内」にありますので比較的、周辺にスペースの余裕があるとはいえ、平地に3000台の駐車場はムリですね。かといって、アリーナ本体を上回るパーキングの建物を建てるのはナンセンス。
そして、那覇市中心部から25㎞程の距離ですが、那覇市内からモノレール延伸・・・ってのも現実的ではありません。
つまりある程度のパーキングスペース整備とともにバスなどでのピストン輸送による送客、その際に発生する交通渋滞対策が最大の課題になるでしょう。
しかし、この「キングスアリーナ」(ワタクシが勝手に呼んでるだけで決まってません)が完成した暁には、日本中の自治体からの視察が相次ぎ、日本中に「エンターティンメント・アリーナ」が増殖する事を期待しております。
エンターティンメントアリーナが増えるという事は、日本バスケも発展するという事です。